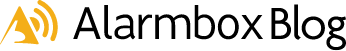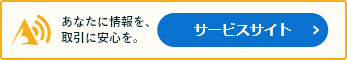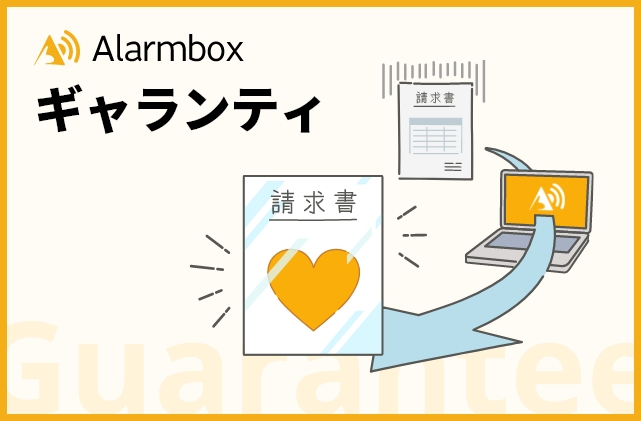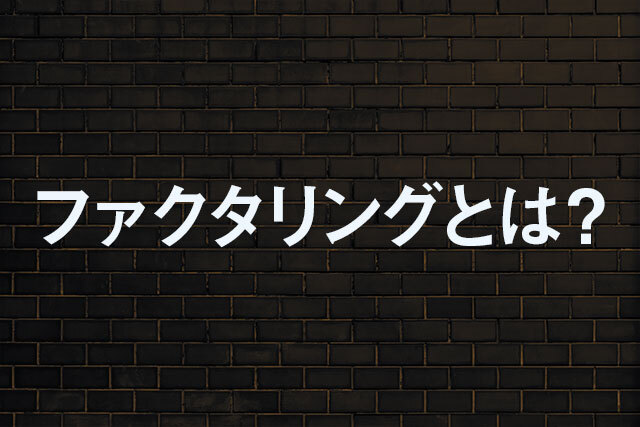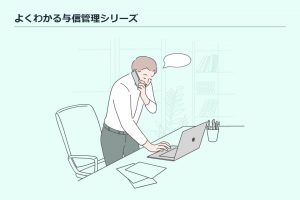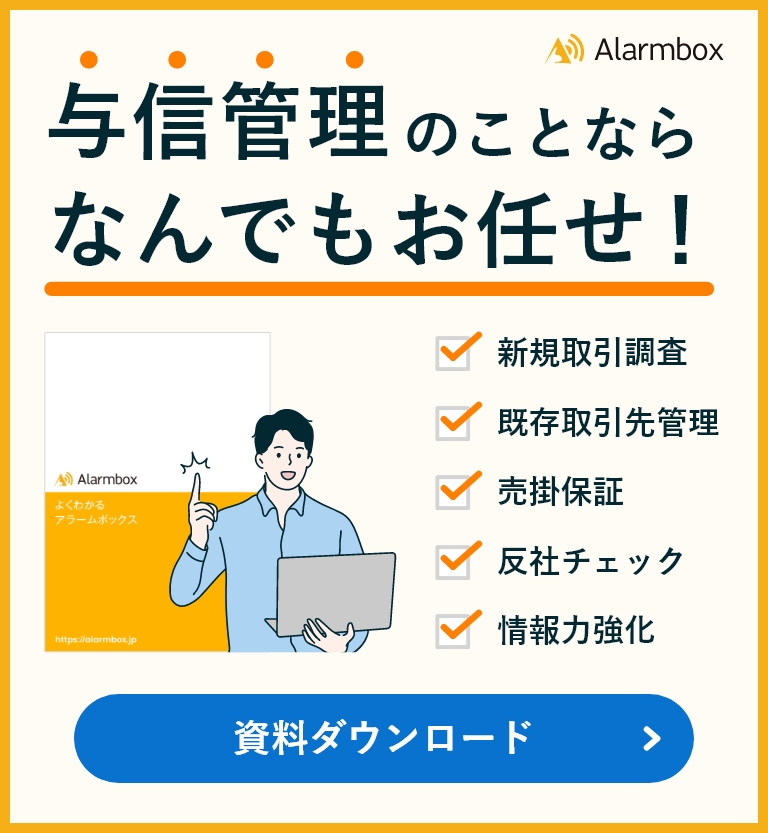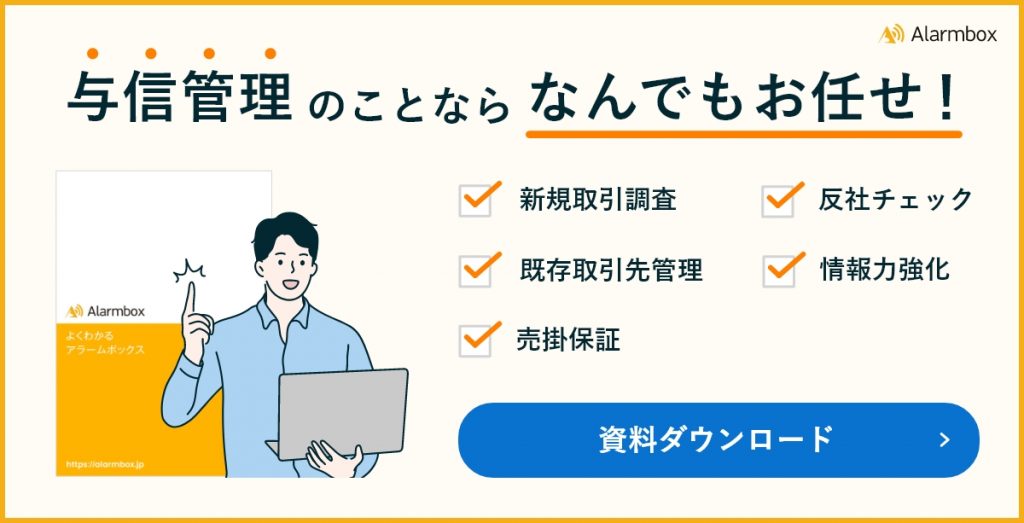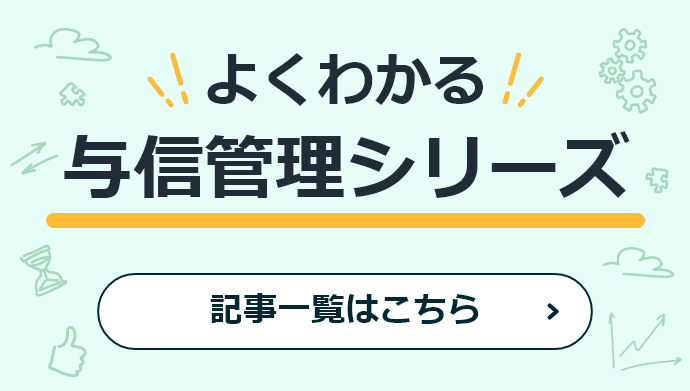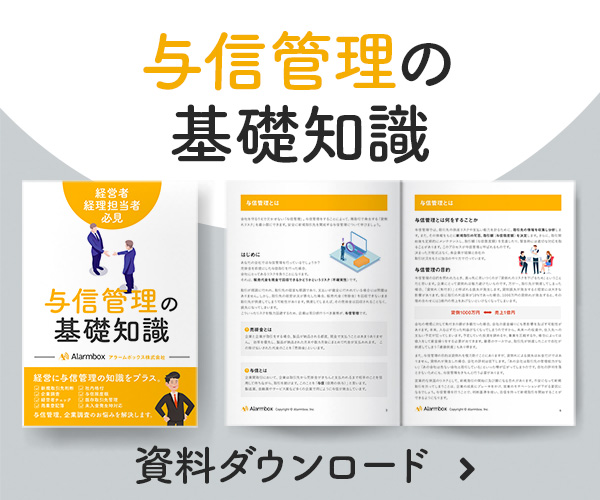どれだけ厳重に取引先を管理をしていても、未回収リスクや倒産リスクはゼロになりません。そこで、取引先の倒産や貸倒に備えて債権を確実に回収するための施策である「債権保全」も行う必要があります。
この記事では、債権の回収を確実にする「債権保全」について、決済条件の工夫や契約書へ記載する項目から、担保の設定や自社で引き受けきれないリスクを外部に移転する方法など、詳しく解説していきます。
目次
債権保全とは
債権保全とは、債権を確実に回収するための施策全般のことです。掛取引を行う上で取引先の未回収リスクや倒産リスクは必ずついて回ります。そこで、与信調査や分析、継続的な与信管理を行い、リスクを最小限に抑えていくことがまずは重要です。しかし、リスクがゼロにならない以上、万が一代金を回収できない場合に備えて対策を打っておく必要があり、これらの施策のことを債権保全といいます。
取引先が倒産し売掛金の未回収が判明した場合、自社と同じ状況の企業が一斉に行動を開始するだけでなく、他社より先に回収行動を行った場合でも「債権者平等の原則」から他社より先に回収できるとは限りません。また、債務超過の場合は債務が資産を上回っているため全社に資産が行き届かず、全債権額の回収は難しい状況となるでしょう。
そこで、他社より先に、かつ確実に債権を回収できるよう、取引条件の工夫や契約書の記載、担保の設定、リスクの移転など、対応を先回りして行っておくことで自社の損失を防いでいきます。
債権保全の方法
債権保全の代表的な施策として以下の方法が挙げられます。
| 債権保全の代表的な施策 |
|---|
|
決済条件(取引内容)を工夫する方法
回収サイトが長いほど代金未回収のリスクが高まります。そこで、支払いサイトの短縮化を行う対応や、支払いサイトが60日の場合、30日で半分の回収、残り30日で全額回収という分割で回収する対応を行います。
また、相手に買掛金がある場合(取引先から商品を購入している場合)は売掛金の一部を買掛金と相殺する対応など、決済条件(取引条件)を工夫しましょう。
取引開始時の条件交渉であれば、取引先も身構えずスムーズに対応してもらえることが多いでしょう。
契約書に条項を記載する方法
信用不安が発生した際、商品や売掛金の回収を直ちに行うことができるよう、契約書の中に債権保全に関する条項を記載します。記載する条項の例として、「期限の利益喪失条項」「所有権留保条項」「契約解除条項」「相殺予約条項」などが挙げられます。 詳しくは契約書について解説している以下記事をご一読ください。
担保権を設定する方法
取引する際にあらかじめ担保権を設定しておく方法です。支払いが滞った際、権利を行使して担保から売掛金を回収することができます。代表的な担保には連帯保証人などの「人的担保」と、不動産や・商品在庫・売掛債権などの「物的担保」が挙げられます。
また、担保取得の際は価格変動の起きやすさや、管理・換金の行いやすさを把握した上で設定します。担保設定時と換金時の価格がかけ離れないように考慮する必要があります。
リスクを外部に移転する方法
売掛金回収には専門的な知識や費用が必要です。また裁判となると長い時間がかかってしまいます。そこで外部の業者を活用し、代金未回収のリスクや裁判にかかるコストを移転する方法があります。 取引先とのトラブルを避け確実に債権を回収する方法として活用されています。リスクを外部に移転する例として、売掛金保証サービス、取引信用保険、ファクタリングなどが挙げられます。
以下では売掛金保証サービス、取引信用保険、ファクタリングについて解説していきます。
売掛金保証サービスによる債権保全

売掛金保証サービスとは
売掛金保証サービスとは取引先に倒産や売掛金の未回収が発生したとき、未回収金の一部または全部の代金を保証会社が支払ってくれるサービスです。
売掛金保証サービスを活用するメリット
活用するサービスによって異なりますが、売掛金保証サービスは主に以下のようなメリットが挙げられます。
- ・未回収リスクを削減できる
- ・与信管理業務の負担軽減
- ・取引先に知られず保証をかけられる
- ・取引先社数が少なくても保証をかけられる
・未回収リスクを削減できる
取引先に倒産や売掛金の未回収が発生した場合、保証会社が代金を代わりに支払ってくれるため未回収リスクがなくなります。倒産や未回収の不安なく取引を行うことができます。
・与信管理業務の負担軽減
取引先の調査は保証会社が行ったうえでサービスを利用するため、与信調査にかかる業務負担が軽減します。また、取引先が倒産した場合、売掛金回収にかかる業務もなくなります。
・取引先に知られず保証をかけられる
ほとんどの売掛金保証サービスは、保証をかけていることを取引先に知られずにサービスを利用することができます。取引先とのトラブルもなく安心です。
・取引先社数が少なくても保証をかけられる
保証依頼を行う企業数が少ない場合でも保証を依頼することができる場合がほとんどです。会社によっては、1社からでも保証をかけることができます。
注意点
与信審査を通過する必要がある
依頼したすべての取引先を保証してもらえるわけではなく、保証会社の審査が通ったもののみ保証されます。あまりにも信用度が低い会社は依頼できないため注意しましょう。
保証対象外の範囲が設定されている
保証依頼時にすでに支払いが滞っていたが申告していなかった場合など、倒産や支払遅延が発生した場合でも保証されないことがあります。 どこまでの範囲が保証されるかしっかりと確認しましょう。
取引信用保険による債権保全

取引信用保険とは
取引信用保険とは損害保険会社が提供する保険の一つで取引先の倒産リスクに備える保険です。売掛金保証サービスと同様に取引先が倒産した際は未回収の一部または全部の代金を代わりに支払ってくれます。 後述しますが取引信用保険の保険対象は倒産のみであることが多いです。
取引信用保険を活用するメリット
取引信用保険には主に以下のようなメリットが挙げられます。
- ・未回収リスクを削減できる
- ・与信管理業務の負担軽減
- ・取引先に知られず保険をかけられる
- ・節税対策
・未回収リスクを削減できる
取引先が倒産し売掛金の未回収が発生した場合保険会社が代金を代わりに支払ってくれます。そのため倒産による未回収リスクを削減することができます。
・与信管理業務の負担軽減
取引先の与信調査は保険会社が行うため保険をかけている取引先の与信調査は必要ありません。また、取引先が倒産した場合の売掛金回収業務もなくまります。
・取引先に知られず保険をかけられる
保険をかけていることを取引先に知られることはありません。取引先とのトラブルもなく安全な取引が可能です
・節税対策
取引信用保険はあくまで保険です。そのため保険料として計上でき会社の節税対策に活用できます。
注意点
保険対象の範囲
取引信用保険の多くは倒産のみを保険対象としています。 利用するサービスによって異なっていますが利用する際はどこまでの範囲をカバーしてくれるか確認しましょう。
取引先の選別
取引信用保険は取引先を包括的にかけるタイプが多く、保険をかけたい先だけ、数社のみの利用はできない場合がほとんどです。 その代わり売掛金保証サービスと比べて保険料率が安い傾向が見られます。
以下は 取引信用保険について詳しく解説した記事になります。ご一読ください
ファクタリングサービスによる債権保全

ファクタリングサービスとは
ファクタリングサービスとは、自社で持っている売掛債権をファクタリング会社へ売却し、売却した金額をすぐに受け取るサービスのことです。 売掛債権を支払期日より前に現金化できるため資金調達の方法としても用いられます。 また、ファクタリングには以下の2種類が存在します。
・2社間ファクタリング
自社とファクタリング会社で完結するタイプの契約です。 取引先に知られることなくファクタリングを利用することができます。 また、2社間のみのため、すぐに現金化することが可能です。
・3社間ファクタリング
自社と取引先とファクタリング会社の3社間で行う対タイプの契約です 2社間ファクタリングよりも現金化までに少し時間がかかりますが手数料が安い傾向にあります。
ファクタリングサービスを活用するメリット
ファクタリングサービスには主に以下のようなメリットが挙げられます。
- ・未回収リスクを削減できる
- ・資金繰りが改善する
・未回収リスクを削減できる
売掛債権を支払期日まで待つ必要がないため売掛保証サービスと同様に倒産や未回収の不安なく取引を行うことができます。
・資金繰りが改善する
債権がすぐに現金化されるため、取引後に支払期日を待たずに現金を入手できます。また、自社の業績が悪い場合でも資金調達が可能です。
注意点
債権譲渡禁止の記載がないか
取引先との契約書に譲渡禁止の項目がある場合ファクタリングは利用できません。取引先との契約書を確認して利用しましょう。
対象外の債権がある
すでに支払いが遅延している債権などのファクタリングは利用できません。
以下は ファクタリングについて詳しく解説した記事になります。ご一読ください
リスクに備えるその他の対策(経営セーフティ共済)

経営セーフティ共済とは
経営セーフティ共済とは、中小企業の連鎖倒産や経営難を防止するための制度です。掛金となる共済金を積み立てることにより取引先の倒産だけでなく急な資金難にも対応しています。
経営セーフティ共済を活用するメリット
経営セーフティ共済には主に以下のようなメリットがあります。
- ・無担保、無保証で借入れが可能
- ・すぐに借入が可能
- ・掛金が損金や経費計上できるので節税が可能
- ・解約しても積み立てた掛金が解約手当金として戻ってくる
・無担保、無保証で借入れが可能
経営セーフティ共済は無担保、無保証人で借入れができます。
・すぐに借入が可能
取引先が倒産したとき、経営セーフティ共済は取引の確認が済み次第すぐに借入れることができます。
・掛金が損金や経費計上できるので節税が可能
経営セーフティ共済への掛け金は損失や費用に計上できるため節税が可能です。
・解約しても積み立てた掛金が解約手当金として戻ってくる
経営セーフティ共済を解約した際、12か月以上掛け金を収めていれば掛け金総額の8割以上の解約手当金を受け取ることができます。
注意点
返済が必要
経営セーフティ共済は借入です。そのため借りた分を返済する必要があります。
解約手当金が利益として計上される
解約した際に戻ってくる解約手当金。解約手当金は利益として計上されるため課税対象となってしまいます。
借入対象外の期間がある
倒産に対する借入は加入後6カ月以上の掛け金を支払った事業者に限定されています。すぐに倒産しそうな会社があるため加入したいといった場合は注意しましょう。
経営セーフティ共済については以下の記事でも詳しく説明しています。
まとめ
今回は債権保全の方法について取引条件や契約書、担保設定、リスクの移転方法などを解説してきました。せっかくの売り上げを損失にしないよう、取引額や取引形態など自社にあったサービスや保全方法を行うことで債権のを確実に回収していきましょう。
※当ブログ記事はリンクフリーです。記事を引用または参考とした場合、出典元として「アラームボックスブログ」の記載および「対象記事URLへのリンク」貼付をお願いします。